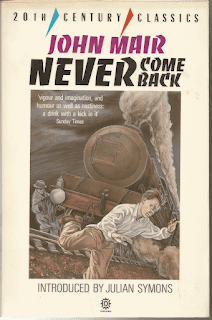ジョン・メア(John Mare)は1913年に生まれたジャーナリストで第二次世界大戦中に戦死し、短い生涯を終えた。本作は彼の唯一の小説で、オフ・ビートなスパイものである。
舞台は1941年のロンドン。雑誌のライターをしているデズモンド・セインが謎の女アン・レイヴンと出逢う。なにが謎なのかというと、まず職業がなにかわからない。そのくせ彼女は金をふんだんに持っているのだ。また彼女の態度もデズモンドには謎だった。彼女はいつも誘っているのかそうでないのかはっきりせず、しかもひどく冷静。男の心を奇妙にかき乱す女だ。デズモンドは彼女の家は知っていたが、日中どこにいくのだろうと跡をつけると、たちまち彼女はそれを察知して行方をくらまし、あとで電話で、またおなじことをしたらもう二度と会わないと連絡してくる。
デズモンドという男は自分勝手でわがままな所がおおいにあり、自分の手に入りそうで入らない女にだんだんいらだちを覚えはじめ、とうとう殺意を抱くにいたる。
数日後に外国へ行くと彼女から言われたある日、デズモンドは彼女の家で彼女を殺害してしまう。
ここからおやおや? という話の展開になる。デズモンドが彼女のアパート出ると、警察よりも早く数名の男たちがその殺害現場を訪れ、死体を発見し、殺害者の調査をはじめるのだ。
じつは彼女は国際的な陰謀組織の一員、スパイであって、男たちは彼女とコンタクトを取るはずだったのに、彼女があらわれないので、家まで様子を見に来たということらしい。
デズモンドはこの組織に捕まえられ、拷問を受け、リストはどこにある、と問われる。そのときはなんのことかさっぱりわからなかったが、組織の人間を二人殺害し逃げのびた彼は、ふとした偶然からそのリストの意味を知り、陰謀組織と虚々実々の駆け引きをはじめる……。
この作品はスパイ小説ではあるけれども複雑な味わいを持っている。シリアスなものとコミックなもの、現実と悪夢、狂気と正気、そういったものがないまぜになって読者を考え込ませる瞬間がいくつもあるのである。「木曜日だった男」ほどの深さはないが、それと似通った哲学的な興趣を持っている。
物語の最後でデズモンドはスパイ組織の親玉の正体を知る。彼は政界・財界における、それなりの大物だったが、しかし「それなり」でしかない。けっして突き抜けた器量の持ち主ではないのだ。彼は本も書いているが、文章もお笑いものだし、内容もくだらない。その程度の人間がリーダーになっているのだ。反体制的な陰謀組織と言うから、モリアーティー教授みたいな、とてつもない悪党がその首領になっているのかと思いきや、じつはまことに凡庸な男でしかない。しかも彼はただ自分が望むことをべらべらとしゃべるだけで、それを実現する末端の人々が味わう現実――たとえば敵の首がへし折れるその衝撃を身体に感じていることや、敵の弾丸に身を貫かれる痛み――を知らない。わたしはデズモンドという男も嫌ないやつだと思うが、彼が最後に味わう感慨には共鳴せざるを得なかった。