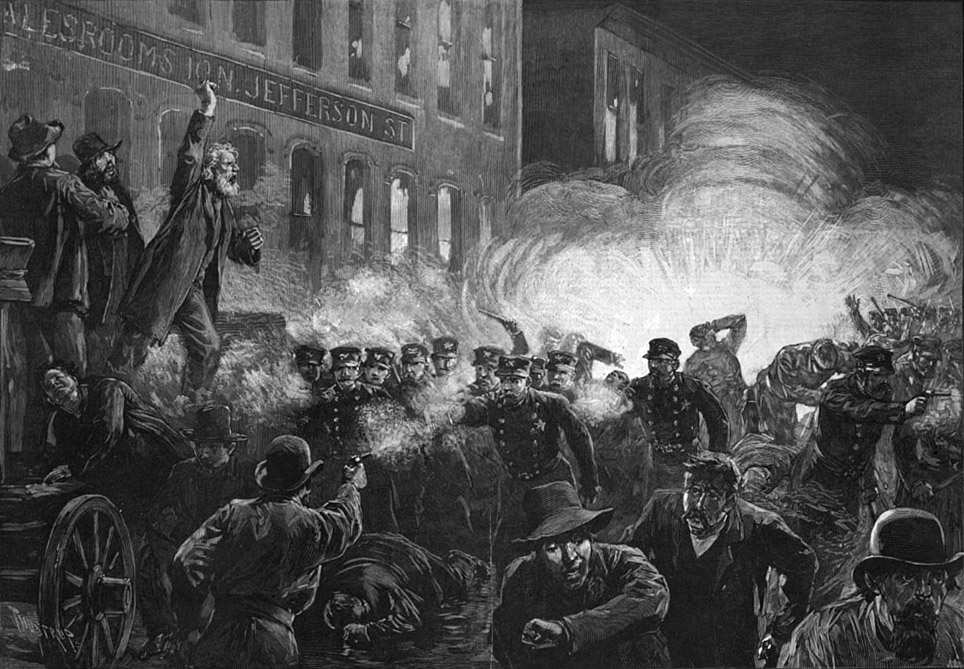5. Der Körper1 des Menschen
der Kopf2
Der Kopf des Menschen ist mit Haaren bedeckt.3
Frauen und Mädchen haben langes Haar auf dem
Kopfe. Männer und Knaben haben kurzes Haar auf
dem Kopfe. Das Haar ist schwarz, braun, rot, blond,
grau oder weiß. Schwarzes und braunes Haar ist dunkel;
blondes und weißes Haar ist hell. Junge Leute4 haben
schwarzes, braunes, rotes oder blondes Haar; ältere
Leute haben graues oder weißes Haar; oder sie haben
kein Haar auf dem Kopfe.
1. der Körper 肉体.
2. der Kopf 頭.
3. bedeckt 覆われている.
4. die Leute (複数形) 人々.
das Gesicht5
In dem Gesicht des Menschen sind zwei (2) Augen.6
In der Mitte des Gesichtes ist die Nase. In dem Gesicht
sind auch der Mund, zwei Lippen, zwei Backen7 oder
Wangen8 und das Kinn.
5. das Gesicht 顔.
6. das Auge 目.
7. der Mund 口.
8. die Backe = die Wange 頬.
das Auge
Das Auge ist schwarz, braun, blau, grau oder auch
grün. Schwarze und braune Augen sind dunkel, blaue
und graue Augen sind hell. Von den Augen sagen wir:
„In den Augen liegt das Herz.“9
9. das Herz 心.
die Nase
Die Nase beginnt zwischen den Augen. Die Nase
endet über dem Munde. Wer zu viel Wein trinkt, hat
oft eine rote Nase.
der Mund
Der Mund ist unter der Nase und über dem Kinn.
Der Mund ist zwischen der Nase und dem Kinn. Der
Mund hat zwei Lippen. Die Lippen des Menschen sind
rot. Wer sehr viel und sehr laut spricht, „hat einen
großen Mund.“
die Backe (die Wange)
Wir haben eine rechte10 Backe und eine linke11 Backe.
Gesunde Menschen haben rote Backen (Wangen). Die
Backen kranker Menschen sind nicht rot.
Wer viel
iẞt, hat häufig dicke oder volle Backen. Wer viel Wein
trinkt, hat häufig volle, rote Backen.
10. recht 右の.
11. link 左の.
das Kinn
Das Kinn liegt unter dem Munde.
Wir sprechen
von einem starken Kinn oder einem schwachen Kinn.
Schwache Menschen haben häufig ein schwaches Kinn.
die Zunge12
Die Zunge ist im Munde. Wenn wir gesund sind, ist
unsere Zunge rot; wenn wir krank sind, ist unsere
Zunge grau. Wer viel Böses über13 andere Menschen
sagt, „hat eine scharfe Zunge.“
12. die Zunge 舌.
13. über: ~に関して; sagen über ~について言う.
der Zahn14
Ein gesunder Zahn ist hart und weiß, ein kranker
Zahn ist grau und dunkel. Mit kranken Zähnen gehen
wir zu einem Arzt, zu einem Zahnarzt. Viele Tiere haben
scharfe Zähne. Die Zähne des Wolfes sind scharf. Ein
Krokodil hat viele große, scharfe Zähne.
14. der Zahn 歯.
das Ohr15
Die Ohren sind an den Seiten des Kopfes. Wir haben
ein linkes Ohr und ein rechtes Ohr. Der Hase und der
Esel haben lange Ohren. Oft sagt man: „Die Wände16
haben Ohren.“
15. das Ohr 耳.
16. die Wand 壁.
der Hals17
Der Hals ist unter dem Kopf. Der Hals ist zwischen
dem Kopf und der Brust.18 Einige Tiere haben einen
dicken, starken Hals, zum Beispiel der Elefant. Andere
Tiere haben einen dünnen Hals, zum Beispiel der
Storch.
17. der Hals 首.
18. die Brust 胸, 乳房.
die Brust
Die Brust junger, starker Menschen ist hoch19 und
breit.20 Die Brust alter, kranker Menschen ist nicht
hoch und breit, sondern schwach. Einige Tiere haben
eine starke, breite Brust, zum Beispiel das Pferd.21
19. hoch 高い.
20. breit 広い.
21. das Pferd 馬.
der Rücken22
Das Pferd und der Esel haben einen starken, breiten
Rücken. Das Pferd trägt23 den Menschen auf seinem
Rücken. Der Esel trägt schwere Säcke auf dem
Rücken.
22. der
Rücken 背中.
23. tragen 運ぶ; 身につけている.
die Schulter24
Wir haben zwei Schultern, eine rechte Schulter und
eine linke Schulter. Wer viel mit dem Körper arbeitet,
hat starke, breite Schultern.
24. die Schulter 肩.
das Herz
Das Herz ist in der Brust. Das Herz liegt auf der
linken Seite der Brust. Wenn wir schnell laufen,
schlägt25 das Herz schnell; wenn wir schlafen,26 schlägt
das Herz langsam. Wenn das Herz still steht, sterben
wir. Von einem guten Menschen sagen wir: „Er hat
ein warmes Herz.“
25. schlagen 打つ.
26. schlafen 眠る.
das Bein
Wir haben zwei Beine, ein linkes Bein und ein rechtes
Bein.
Wer viel geht, läuft, tanzt oder springt, hat
starke Beine. Wer sehr wenig geht, läuft, tanzt oder
springt, hat weniger starke oder schwache Beine. In
Deutschland sagt man nach dem ersten27 Glase Bier
oder Wein: „Auf einem Bein kann man nicht stehen,“
und dann28 trinkt man ein zweites27 Glas. Wenn jemand29
etwas30 vergißt,31 sagt man: „Was man nicht im Kopf
hat, muß man in den Beinen haben.“
27. erst 最初の; zweit 二番目の.
28. dann それから.
29. jemand 誰か.
30. etwas 何か, いくらか.
31. vergessen 忘れる.
der Fuß32
Wir haben zwei Füße, einen linken Fuß und einen
rechten Fuß. Eine Katze fällt immer auf die Füße.
Wenn jemand viel Glück33 im Leben hat, sagt man:
„Er fällt immer auf die Füße.“ Wenn jemand ein
großes, schönes Haus hat, viel Land und viel Geld, sagt
man: „Er lebt auf großem Fuße.“34 Wenn man gut
versteht, was ein Freund spricht, sagt man zu seinem
Freunde: „Was du sagst, hat Hand und Fuß.“
32. der
Fuß 足(くるぶしより下).
33. das Glück 運, 幸福.
34. er lebt auf großem
Fuße ぜいたくな暮らしをする.
die Hand
Wir haben zwei Hände, eine linke Hand und eine
rechte Hand. An jeder Hand haben wir fünf Finger.
Mit dem Zeigefinger35 zeigen35 wir. An dem Ringfinger
tragen wir einen Ring. Man sagt: „Eine fleißige Hand
macht reich“;
-- „Er hat eine glückliche Hand"; --
„Er ist in guten Händen.“
35. zeigen 見せる, 指し示す; der Zeigefinger 人差し指.
das Knie
Wir haben zwei Knie, ein linkes Knie und ein rechtes
Knie. Das Knie ist in der Mitte des Beines.